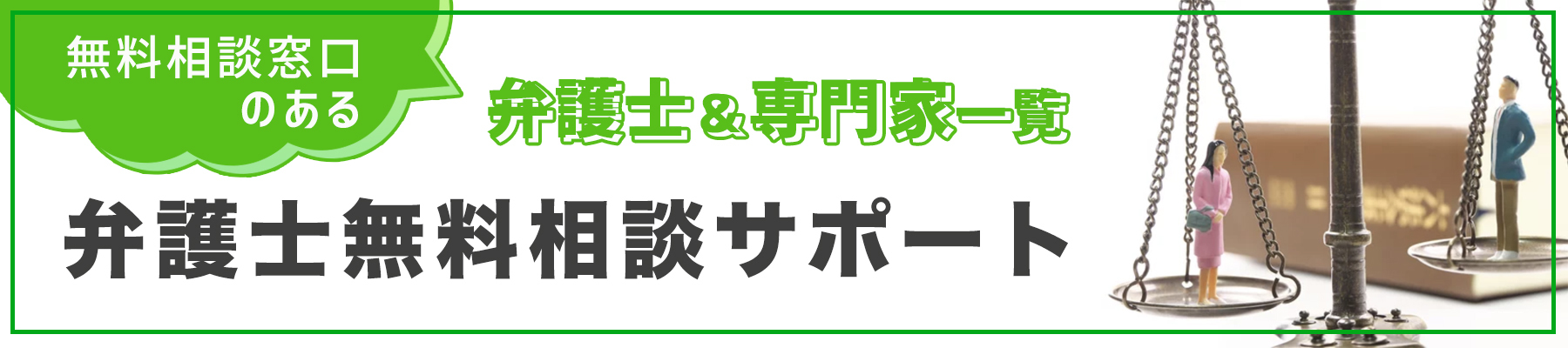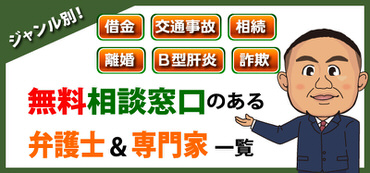改正貸金業法完全施行の効果について
改正貸金業法は、平成18年に公布され、平成22年6月に完全施行されました。
この改正には、グレーゾーン金利の廃止と、収入の3分の1以上の貸付の禁止が盛り込まれました。
この改正により、多重債務に関する問題が大幅に改善しました。
日本弁護士連合会は、改正法の完全施行から3年後の平成25年6月18日に、会長声明を発表しました。
この声明によりますと、法改正時(平成18年)には、5社以上の消費者金融業者に借金をしていた多重債務者が約230万人おりましたが、この数は、平成25年には、約29万人に激減しました。
同じく、平成18年には約17万人いた自己破産者が、平成25年には約9万人に減りました。
さらに、多重債務による自殺者も、法改正時の1973人から平成25年の839人とほぼ半減しました。
自殺者全体の数でも、平成24年は前年比でマイナス9.1%と大きく減少し、15年ぶりに3万人を割り込むなど、大きく改善しました。
この背景には、この貸金業法の改正により、多重債務による自殺者が大幅に減少したことが、その大きな要因として考えられています。
このように、平成22年6月に完全施行された改正貸金業法により、多重債務者の問題は劇的に改善しました。
相談を受けて現実を知った司法書士の功績
多重債務の被害者のため相談所で、ボランティアで協力している司法書士の話によると。
最初、その司法書士は「多重債務に苦しむのは、基本的には無計画にお金を借りて返せなくなった債務者が悪い」と考えておりました。
しかし、相談業務をしているうちに、「本当に悪いのは弱いものを食い物にする業者の方だ」と考えが変わったそうです。
また、平成18年1月に、グレーゾーン金利の適用を実質的に無効とする最高裁判所の判決が出されました。
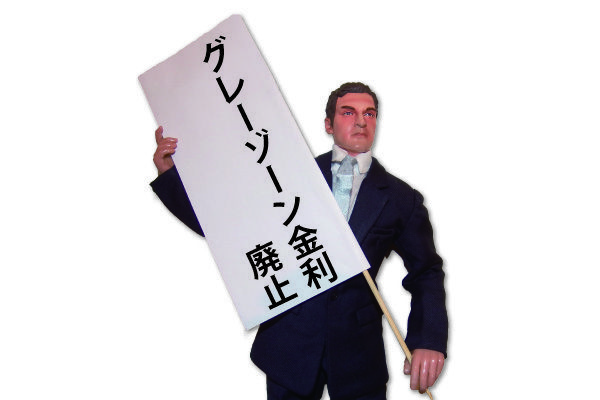
この判決は、貸金業法の改正によってグレーゾーン金利が実質的に廃止されるのに重要な役割を果たしました。
この判決を下した最高裁判所の裁判官が、退官後、次のように述べています。
「消費者金融が空前の利益を上げる一方で、小売のために自殺者が出ているのは、どこかおかしいと考えていた」と。
法律制度の改正の背景
貸金業者の中には、トイイチといって利息が10日で1割(年利365%)や、3万円借りて10日後に5万円を返す(年利2,433%)もの。
5万円借りて10日後に7万円を返す(年利1,564%)ものなど、明らかに法律違反の金利を貸してくるところもあります。
ただし、このような業者に対しては、明らかな法律違反をしています。
債務者が専門家に相談することさえできれば、その取締りは比較的容易だと言えます。
しかし、グレーゾーン金利の上限金利(貸付額に応じて21.9%〜29.2%)で合法的に貸し付けを行う大手の消費者金融業者に対しては、法改正があるまでは、それによる多重債務者に対しては、何らの救済措置もありませんでした。
実に多くの方々が、それらの合法的に高利貸を行う消費者金融業者に苦しめられました。
また、これらの業者は、過剰借入れを誘発しやすいリボ払い方式を同時に採用しますから、高金利による被害はますます大きくなりました。
被害の大きさという点に関しては、ヤミ金業者と言われる違法な高利貸したちよりも、こういった合法的かつ計画的に多重債務者を発生させる大手消費者金融業者の方が、はるかに悪いことをしているとも考えることもできます。
しかし、改正貸金業法の完全施行により、グレーゾーン金利の廃止と、貸付額の総量規制が設けられました。
これにより、特に、空前の利益を上げていた大手消費者金融業者が、一斉に、利息制限法の上限利率を超える利息を取ることが禁止されました。
多重債務の問題を発生させる一番の原因に司法のメスが入りました。
これが、多重債務に関する問題を劇的に改善する要因となりました。
10年ぐらい前には、当時はサラ金といっていましたが、消費者金融による多重債務者に関する悲惨な事件のニュースが連日のように報道されておりました。
ところが、最近は、めっきり、そのような報道を見聞きすることがなくなりました。
その背景には、このような消費者金融に関する法律制度の改正があったというわけです。
このように、法改正があり多くの債務者が救済されるようになりました。
しかし、現実では個人で解決するのは難しい問題であることは確かです。
借金に関する問題をあなたも抱えているのなら、まずは、専門家に相談することをお勧めします。